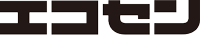『これが日本の自然体験~エコセン世話人が独断で選ぶ日本の自然エリアと体験~』第12弾(山本かおり )
『ザ・小笠原』
今から23年前。2002年3月に、専門学校の仲間と共に小笠原へ自然観察に行きました。
その頃私は、自然を守る技術を学ぶ専門学校に通っていて、自分より若い仲間たち6人を引き連れて、竹芝桟橋よりフェリーに乗りました。
24時間以上海の上にいて散々な船酔いを経験し、陸地に降り立った時にはまだ船上にいるような感覚でした。

小笠原には4日間滞在しました。父島と母島のうち、この時は父島のみに絞りました。
(小笠原に行くには、おがさわら丸というフェリーに乗って、5泊6日の行程です。)
着いたその日は、ビジターセンターに行ったり、三日月山でホエールウォッチングをしたり、ちょうど開かれていた「小笠原フォーラム2002―アジア・太平洋の自然と人間 持続可能への模索―」(第一部)に参加したりしました。
2日目は、私は亜熱帯農業センターと小笠原フォーラム(第2部)に参加し、他のメンバーはジョンビーチへハイキングや釣り&サイクリング(スクーター)にでかけました。
夜はマルベリーの吉井さんというガイドに依頼して、ナイトハイクをしました。
翌日も一日、吉井さんに島を案内してもらい、様々な生き物や小笠原の特徴などについて説明してもらい、勉強しました。
最終日は、ホエールウォッチングや海洋センター見学、散策など各々楽しみました。
小笠原滞在中、私たちはずっとフェリーに宿泊しました。(雑魚寝状態。そういう安いパックがありました)
※参考:マルベリー

私は専門学校時代、生き物や自然環境だけでなく、それらと関わる人の暮らしにも興味を持っていて、当時の報告書にこんなメモを残していました。
【小笠原の暮らしについて】
小笠原と本土を結ぶおがさわら丸が、1週間に一度東京から物資を島に運んでいる。
島では農業も営まれているが、食料のほとんどを本土からの輸送に頼っている。
最近では電気や水道が島のすみずみまで行き渡るようになったが、一昔前までは島の一部(港周辺の人口が集中している地区)にしかなかったそうだ。
小笠原では民間のアパートを借りると東京並の家賃(7万円/ワンルーム)で、移り住んでくる人には住みにくい環境であるが、都営住宅に入ることができれば大分暮らしやすくなる。小さな島なので仕事がなく、公共事業に頼りきっている。

この時参加したフォーラムでは、国内外の大学の先生や小笠原野生生物研究会の方などのお話を聞いたり、地元の方が発言されたりして、とても刺激になりました。
小笠原で見られた生き物の中には外来種が混じっていることや、島が公共事業で傷だらけになっていることも実際に見て実感もしました。 23年たって、今はどうなっているのか、久しぶりに小笠原を訪れてみたくなりました。

【エコセン事務局 / NPO法人ゆいツール開発工房(ラボ) 山本かおり】
コラム「Go to にっぽん」の一覧はこちら。
コラム「スペシャルな『旅の話』」の一覧はこちら。
コラム「サステイナビリティを主張!」の一覧はこちら。