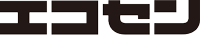『これが日本の自然体験~エコセン世話人が独断で選ぶ日本の自然エリアと体験~』第17弾(吉田 直哉 )
『音威子府(おといねっぷ)』
利尻島で登山道を語る前編からの続きです。
弾丸登山明けでフェリーや列車は爆睡、寝過ごしをかろうじてこらえ、
夕刻、僕は宗谷本線の小さな駅に下り立った。

音威子府村は住民約600人、北海道でいちばん人口が少ないというこの地は「森と匠のむら」。
盛んだった林業に加え、アイヌの彫刻家砂澤ビッキ氏がアトリエをかまえたことが、
村おこしの取り組みの発端だという。

ここで森のクラフト体験施設を作るなら珍しくもない話だが、この村は、専科の高校を作るというユニークな取り組みを始めた。
北海道おといねっぷ美術工芸高校。
廃校も噂されていた村立高校を転換したのである。
村の子が進学しない高校の改修に多額の税金を投じ、住民税も払わない高校生を集めるのが、はたして地域おこしなのか?
一時は村を二分する議論になったという。
が、始まってみれば毎年新住民40人、その全員が才気あふれる若者たちだ。
工芸教室や運動会での村民との交流、震災復興支援や国際交流では生徒たちが村をリード。
いつしか村人はサポーターに転じ、この高校はいまや、全国からの志願者で倍率2倍超の難関高。
あそこの子たちはすごいよー、夕飯食べたらまた学校戻って製作の続きをしてるって。
と、これは宿で聞いた評判だ。
その原点でもあり、いまも生徒たちがボランティアに通うというビッキ氏の元アトリエは、隣の筬島(おさしま)駅にある。
実は今回、登山で日程がずれて行きそびれたので、写真は10年前のもの。
森の息づかいを感じるような、荒々しくも繊細な作品たち。
光と影が交錯する大人の空間。
窓の外に目を向ければ広大なかぼちゃ畑と、天塩川の原始の流れ。
停まる列車は1日3往復という無人駅と、離農した廃屋が目立つ集落に、キセキのようなミュージアムがある。
必見ですよ!

実は僕はこの村を、40年近く前に何度か訪れている。
大好きだったローカル線・天北線の分岐駅だったから。

そして乗り換えの時の楽しみが、名物、常盤軒の駅そばだ。
そばの実を丸ごと挽いたという黒い麺は、日本一の駅そばとして親しまれた逸品だったのだ。
天北線廃止で客が激減した後も常盤軒さんは頑張っていた(観光地には縁遠い過疎の村に駅そば屋があること自体があり得ない話で、
それだけファンが多かったのだろう)。が、4年前、店主の死去によりついに終止符が。
それを追うように、村で唯一の製麺所も閉鎖してしまった。
村人にも旅人にも愛された名物を何とか復活できないか。
その声にこたえたのが、村に移住しゲストハウス兼満福食堂・イケレをはじめたTさんだ。
製麺所の元オーナーに製法を請い、古い機械を直して試行錯誤、ついに食堂メニューに復活させたのだ。
イケレに泊まった僕らも、夕食に真っ黒いおそばをいただく。
香りもコシも強い独特の風味が、口の中いっぱいに。
食堂では旅人同士、天北線の話題でも話が弾んだ。
学生時代、こうして旅仲間を作りながら北海道を巡った日々を思い出す…。

吉田さん40年前から音威子府そばを知ってるんだ、うれしいなあ、と言って、翌朝Tさんがわざわざ出してくれたのは、最北の駅そばの幟。

なんと、村が公募したチャレンジ事業として、この夏、週末限定で駅そばも復活させるのだそう。
オンリーワンの取り組みで頑張っている村と、この地に恩返しをしたいという移住者の心意気がかみあった奇跡。
「イケレ」とはアイヌ語の「感謝」からいただいたという。
小さな一歩だけど、この素敵な響きを持つ村が、道北の希望の星になりますように。
頑張れ!
心からエールを送りつつ、40年前と変わらない懐かしのホームから、旭川行の列車に乗り込んだ。
【エコセン監事 / NPO法人丹沢自然学校理事、神奈川県自然環境保全センター 吉田 直哉】
コラム「Go to にっぽん」の一覧はこちら。
コラム「スペシャルな『旅の話』」の一覧はこちら。
コラム「サステイナビリティを主張!」の一覧はこちら。